
まず、ランブラス通りを横に入ったホテルから歩いて近いグエル邸。
ガウディー初期の傑作といわれている作品ですが、残念ながら改装工事中のため中を見学することはできませんでした。1階周りも仮囲いがされていて、外側から上部を望むのみでした。
バルセロナのシャンゼリゼ通りと呼ばれ、カタルーニャ広場から北西に延びるグラシア通りを北上して点在するモデルニスム建築を巡りました。
スペインを代表するグランドメゾンのロエベの入ったCasa Lleo Moreraカサ・リェオ・モレラは、20世紀の初頭にガウディー以上に名声を博したといわれる天才建築家のドメネク・イ・モンタネールの作品です。彼は「花の建築家」といわれ、花柄のタイルや装飾が多用されています。
同じブロックの数軒先にあるのが、ガウディーのCasa Batlloカサ・バトリョ。
オーディオガイド込みの入場料で日本語もあります。充実したガイドを聴きながらの見学は感嘆することが多く、たっぷり時間をかけて観ました。
風が通り抜けるようにドアに設けられたガラリや、光の拡散で室内をやわらかくする効果を狙った窓など。
海をテーマとし、青を基調としたこの建物では、階段室の吹き抜け上部のトップライトから入る光の量の差で色が同じに見えるよう、上部は濃く、下階ほど青が薄くなっています。窓の大きさも上部は小さく、下は大きくなっています。
直線のない自然の植物や動物の骨などをモチーフとし、複雑なデザインの中で細部に亘り機能面までよく考えられています。手の握りににあわせたドアハンドルは、ブローチにでもしたくなるような美しいフォルムだし、この最上部の洗濯部屋と物置のある階は、雨は入らないけれども光を入れつつ、湿気がこもらないように風が抜ける仕組みです。動物の骨を思い起させる形状です。
煙突は集約してデザイン的に見られるようにしています。
模様をかたどるモザイクに見えるタイルは、割れた陶器やタイルを再利用したものです。
風や光の取入れ方などに加え、今や盛んに建築界で行われている環境に配慮した建築的な提案が既になされていた建物であることに感銘しました。
次は、同じ通りを北に進み、Casa Milaカサ・ミラ。
石を積み上げたような形状から石切場を意味する「ラ・ペドレラ」とも呼ばれています。
こちらは、山がテーマ。
最上階がガウディー建築に関する展示室になっています。
これは、チェーンをつり下げた模型、屋根の構造を検討したものです。
この下には鏡が置かれていて、まさに逆さまに置くと、屋根の形状が見えてきます。
このつり下げられた模型で検討された建物の模型も飾られています。
アパートの一部や屋上も見学できて、段差のある"山"のような屋上面からバルセロナ市内を一望できます。
東方向に道をたどると着く次の目的地、サグラダ・ファミリア聖堂も見えます。
ガウディーの死後、今も尚、建築工事が進められているサグラダ・ファミリア聖堂には、大きなクレーンが設置されています。
昨年11月に聖堂内が完成し、ローマ法皇が訪れてミサが行われ献納されてから、年末年始のミサも合わせて内部がテレビ放映されるようになり、内部に入ったことのなかったバルセロナ市民の間で、「これはもはやガウディーの建築ではない」「このまま建築工事を続けて完成させるべきだ」など論争が巻き起こっているというサグラダ・ファミリア聖堂です。
バルセロナにいる間に観た現地のニュースでも聖堂の映像が流れ、市民や建築家などに意見をインタビューする様子が流れていました。日本人彫刻家の外尾悦朗氏の指導のもと、損傷を受けた彫刻の修復や未完成部分の石膏模型を使ったワークショップが行われているのが、地下の展示場で見ることができます。
ガウディーの生前に完成した東側の「生誕のファサード」を観ていると、その精巧なつくりと、年季の入った色合いと比べて、確かに新しく完成した部分は、ハリボテのように見えるという意見もうなずけます。しかし、1882年に着工以来実に120年近く、世代を超えて今も尚建設中の長大なロマンをこのまま続けてもよいのではないかと、私は工事続行に賛成ですが、今後論争はどう展開していくでしょうか。




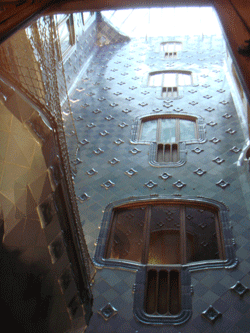



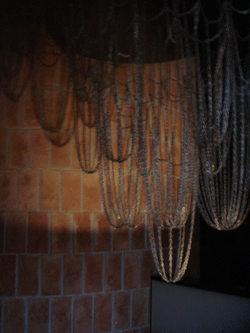
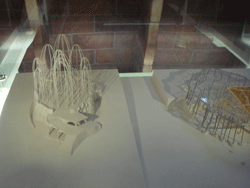


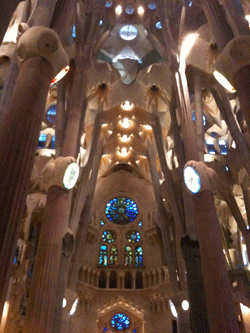


コメントする