
くさり橋の向こうに見える、銅板屋根のある建物が王宮。
「王宮のある丘」へ上るといいたいところですが、ハンガリーでは、丘全体が王の城域であったことから「王宮の丘」とはいわず、この丘全体をさして、ヴァールVar(城、宮殿の意味)というそうです。
前述の建物自体も、「ブダ城の宮殿」、「王の宮殿」とハンガリー語で呼ぶのだとか。
今日はこの王宮へのぼりました。

行きは、丘の麓から出ているケーブルカーに乗りました。
王宮は、広い丘で、今では土産物屋や飲食店が並ぶ普通の路地もあります。
町の美化計画の一環としてつくられたという、戦いのためではないのに「漁夫の砦」
かつてここに魚の市が立っていたことや、城塞のあたりはドナウ川の漁師組合が守っていたことなどが、名前の由来になったようです。
ここから眺めるペスト地区も絶好です。
「ブダペストのシンボル的な存在」と紹介されているマーチァーシュ教会。
音響効果が優れていることでも知られ、かつ内部にあるステンドグラスや宗教画、石像などは美しいそうですが、17時までとガイドブックに書かれていた見学可能時間が、14時半までと張り紙がされており、残念ながら中に入ることができませんでした。
街中に戻り、ハンガリーのデザイナーがつくる衣料・小物を扱うお店
同上のデザイナーたちと同期で学んだという帽子デザイナーのお店。
魅力あるお店のオーナーが教えてくれた建築を扱うギャラリー兼書店に足を運びました。
地下のハンガリーの建築展もさることながら、1階で展示されていた年ごとのハンガリーが生み出した数々のプロダクトデザインの中には、ルービックキューブが。
一世風靡したあの名作はハンガリー産だったとは、つゆ知らず。
実家のどこかに転がっているであろうルービックキューブをまたいじりたくなりました。
そして、今日の温泉は、ゲッレールトの丘の王宮側の麓にへばりつくようにある、ルダジュ温泉。
オスマントルコ統治期の1566年につくられたというトルコ式の浴場です。
従来、温泉は男性専用だったそうで、今でもここの温泉に女性が入ることができるのは、女性のみの火曜日か、混浴の土・日だけ。
色ガラスから漏れる光が美しいドーム型の天井の下にある八角形の浴槽で、当時の雰囲気を想いはせながら長湯しました。


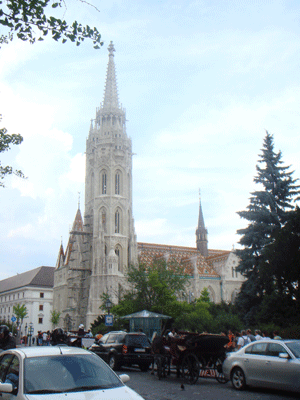





コメントする